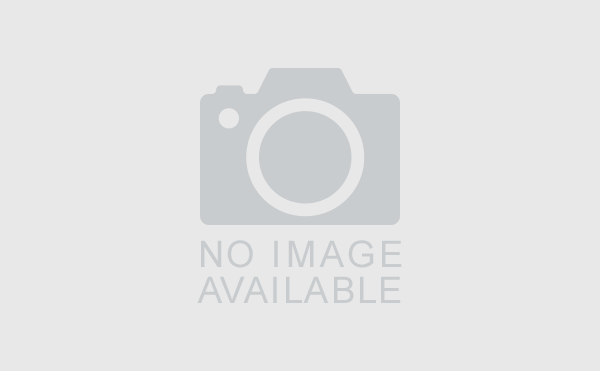サードステージのヒント
最近サードステージのヒントになる本を見つけました。野口悠紀雄さんの書かれた「83歳、いま何より勉強が楽しい」です。
これは2024年に出版された本ですが、執筆された時点で野口さんは83歳です。私は、人生は28年毎にステージが変わるというLIFE STAGE 理論というのを考えていますが、56歳で終えるセカンドステージまでは、自分で経験したので何となく分かっていました。しかし56歳から84歳まで続くサードステージは、現在自分がその真っ只中にいて(現在67歳です)、どう過ごしたらいいのか仮説検証を繰り返しながら手探りをしている状況です。現在サードステージの4割の期間が過ぎて、サードステージがどんな時代なのかはおぼろげに見えてきましたが、まだ確信は持てていない状況です。今回サードステージの大部分を経験された野口さんの書かれている本でしたので、いろいろと参考になりました。
野口さんの活動量が驚異的なのは、(それ以前も数多くの本を執筆されていますが)83歳になってからの1年間(つまりサードステージの最後の1年)で次の5冊の本を執筆、出版されたことです。
①「生成AI革命 社会は根底から変わる」(2024年1月発売)
②「ChatGPT「超」勉強法」(2024年3月発売)
③「日本の税は不公平」(2024年3月発売)
④「83歳、いま何より勉強が楽しい」(2024年4月発売)
⑤「アメリカはなぜ日本より豊かなのか?」(2024年8月発売)
野口さんは元々経済学がご専門の大学教授をやられていた方なので、③④⑤を書かれるのは分かりますが、①②の最新技術の分野までカバーされているのは驚きです。
この本の内容は、私がサードステージを11年やってみて感じていた仮説を裏付けることがいろいろと書いてあり、やっぱりそうだったかというのが読み終えた感想です。
以下、本文から特に参考になった部分を抜粋していきます。
*************************
『人生100年時代が現実のものとなりつつあること、そして、60歳代以降の定年退職後の生活が重要になってきました。この期間は、これまでは、働いた後の余生と考えられていたのですが、そうではなく、セカンドライフとかセカンドキャリアと言われるように、この期間こそが人生の最も素晴らしい、重要な時期になったのです。そのように、考え方を転換する必要があります。しかし、この時期を実り多いものにするのは、それほど簡単なことではありません。そこで、勉強を生活の主軸にすることを提案します。』
『この期間についてしばしば問題とされるのは、退職後生活の経済的な問題です。これが重要問題であることは間違いありません。ただ、それだけではなく、精神的な面も重要です。そして、その面において最も有効なことが、勉強なのです。何かのためでなく、勉強することそれ自体が楽しいから勉強する。そのようなことが実現できる贅沢が可能な時代になったのです。』
『シニアの勉強は最高の贅沢。自分のための勉強をすることで、この期間を、人生の黄金時代とすることができます。』
➡️私はLIFE STAGE 理論で、サードステージ (56歳~84歳)を 人生を愉しむステージ、具体的には真理を求める時代と定義しています。「真理を求める」=「勉強する」と考えると、この定義で良かったんだと思いました。
『好奇心は勉強の最大の原動力。知識が増えると、好奇心が高まり、さらに勉強したくなります。』
➡️年齢が高くなっても面白い人の共通点として、好奇心が旺盛だということを感じます。好奇心を持ち続けるって大事ですね。私も好奇心が減衰しないよう心がけようと思います。
『おおよその骨格が頭の中にすでにできている段階で、スマートフォンに向かって原稿の口述筆記をすると、20分程度散歩すれば2000字位の原稿は簡単にできます。ただし、この方法を行う場合、重要な注意があります。それは散歩を始める前に頭の中を問題で一杯にしておくことです。これから考えなければならないこと、整理しなければならないことで頭を一杯にします。歩いているうちに、それの答えが生み出されるのです。頭に材料を一杯に詰め込んでから散歩すると、「材料が頭の中で攪拌されて」発想ができるような気がします。新鮮な空気が脳を活性化するのかもしれません。足の刺激が発想を促進するという説もあります。少なくとも、体を動かすことは、発想にプラスの影響を与えるようです。「歩く」ことは、アイディアを得るための、最も手軽で最も確実な技術です。私は凝り固まった問題が頭の中にあって、歩くとそれが分解されて、うまい形に組み直されるのだというようなイメージを描いています。』
『重要なのは、散歩の前に頭を一杯にしておくことです。それがなくては、息抜きに終わります。私の経験は、それを強く裏づけます。本の執筆中には、散歩すれば必ずアイディアが出てきます。しかし、集中した仕事をしていないときには、単なる散歩に終わります。頭がカラでは、いくらゆさぶっても、何も出てこないのです。頭の中が空っぽの状態で散歩を始めても、ただ散歩をするだけで、何の成果も得られません。考えてみれば当然のことですが。』
➡️私も、コロナ禍をキッカケとして、長時間の散歩をするようになりました。やってみて意外な発見は、歩くといろいろなことを閃き、新しい企みが生まれるということです。まさに野口さんが書かれているのと同じような経験をしました。ただし「散歩を始める前に頭の中を問題で一杯にしておくことが大事だ」ということには気が付きませんでした。
以上が、この本に記載の内容で特にいいなと思った点ですが、本に書かれていてやってみると面白そうだけどまだやっていないのが次の2つです。
・散歩中の音声入力による原稿作成
・ChatGPTとの雑談
この2つができるようになると、また面白いことに繋がるのではと予感しています。もし、これができるようになった暁には、感想(うまくいくためのコツ)をレポートしたいと思います。