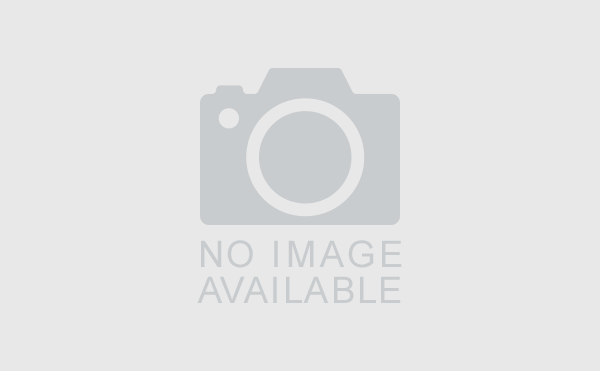お勧め就活本
私がJTで初めて採用担当になったのが入社6年目の1987年10月でした。それ以来、あるときは採用担当、あるときはリクルーター、あるときは面接官と立場は変われども、ほぼ毎年就活生と会ってきました。現在も「J-CAD」という就活生の選抜コミュニティを運営していますので、いまだに学生と会っています。(笑)
そのため、本屋に行くと就活本コーナーに立ち寄り、何か学生にお勧めの就活に役立つ本はないかと見てきましたが、なかなかこれはいいという本はありません。ほとんどはテスト対策や面接対策本で、就活の本質的なことに切り込んだ本ではありません。長年 (約40年) 就活関連の本を見てきましたが、その中でこの本はいいことが書いてあるなと思った本が2冊あります。本日はこの2冊を紹介したいと思います。ともに就活生の常識とは違うことが書いてあります。
1冊目は海老原嗣生さんが書かれた次の本です。海老原さんは、元リクリートエージェント(当時はリクリート人材センター)の転職アドバイザーで、週刊モーニングに連載され、テレビ朝日でドラマ化もされた漫画「エンゼルバンク」のカリスマ転職代理人、海老沢康夫のモデルになった人です。2011年に出版された本ですが、今読み返してもなるほどと感じることが書いてあります。

本の帯に書いてある次の言葉がこの本のエッセンスです。
『「仕事内容」で就職先を選ぶべからず。』
本の中から一部抜粋します。
『社風や会社のカラーで、就職を決めた人は、どんなに異動があっても、それなりに馴染んで会社生活を送ることができます。ところが、仕事で会社選んだ人は、どこに異動しても浮かばれない (つまらない) 毎日となる……。
日本型雇用の利点でもあるこの当たり前の事実が、あまりにも軽んじられてきました。
私はここに異を唱えたいのです。俗に「就社ではなく就職を」と声高らかに謳う就活指導が全盛ですが、そんなもの、クソ食らえでしょう。』
『日本型雇用とは、社内で自由に移動ができ、それにより再チャレンジが促される仕組みです。これは欧米型キャリアでは非常に実現しづらい、日本独特のよい仕組みといえるでしょう。この特典のある社会なのに、なぜ「会社」ではなく「仕事」で就職決めろというのでしょうか。キャリア教育や就職指導をする人たちが、そう語る理由がわからないわけではありません。多くの学生は、意味もなく人気企業を受けたがる。「そんな空虚の人気だけで、企業を選ぶよりは、仕事をよく見なさい」ということが、「会社」ではなく「仕事」と言う風潮を作ったのでしょう。その流れ自体は悪くは無いのですが、本当なら「そんな”空虚な人気”ではなく、”社風や風土、価値観があなたに合っているかどうか”を見なさい」とここまで言うべきでした。社内再チャレンジを繰り返せる反面、思った職務にはつけないという、日本型雇用の仕組みを踏まえて語れば、その方が合理的な職場選びです。』
要は、社風の合う会社に入るのがいいという内容ですが、本書には社風をどうやって見分けるかという具体的な方法も記載してあります。(社風の見分け方を具体的に解説している本はおそらく他にはないと思います。)
さらに、業界毎の入社後のリアルな姿を解説してあるのもいいですね。今人気の商社やコンサルに入った後のリアルな姿が分かります。
例えば、商社の強さの本質を次のように分かりやすく解説してあります。
『では商社の本来の強みとは何でしょう? 私はそれを、「何とかしてしまう力」だと分析しています。』
『「何とかする力」同様に、もう一つ大きな力を彼ら持っています。それは、「誰かと誰かをくっつける力」「束ねる力」とも言えるものです。』
『ネット時代だからこそ、ネットで解決できない高度な問題について、「調整しながら」「何とかする」役割が重要視されているのです。』
その他の業界の仕事についても、学生目線とはまったく違う角度から解析して、分かりやすく解説してあります。
この本は、学生が就活の間違った常識に陥らないために、就活を始める際に読んでおくといい本です。
もう1冊はマッキンゼーの採用マネージャーを12年務められた伊賀泰代さんが書かれた次の本です。こちらも出版は2012年と古いですが、本質的ないいことが書かれていて今読み返しても参考になります。タイトルからはマッキンゼーの採用方法について解説した本のように見えますが、実は業界にかかわらずビジネスパーソンに必要な力、リーダーシップについて解説してあります。
マッキンゼーが求めている人材は「将来、グローバルリーダーとして活躍できる人」で、見ている要素は次の3点です。
①リーダーシップがあること
②地頭がいいこと
③英語ができること
この点で就活生に誤解があると指摘されています。
『マッキンゼーをはじめとする外資系コンサルティング会社は、とにかく頭のいい人を求めている」と思われているのです。 しかもその「頭のよさ」とは、学歴が高いことやケース問題がスラスラと解けることだと解釈されています。最近よく聞く〝地頭〟という言葉も、フェルミ推定など、特定の問題解決手法を使いこなせることと同義のように語られています。しかし採用の決め手になるのは、地頭でもケース問題の正答率でもありません。』
『卒業大学名はスクリーニング基準としては使いやすい要素だが、採用基準にはならない。反対にリーダーシップ・ポテンシャルの有無は重要な採用基準ではあるけれど、スクリーニング基準としては不適切であるため、採用基準として重視されていることが外部から見えにくい。』
要は、地頭がいいだけの学生を採ろうとしているのではなく、リーダーシップ・ポテンシャルもある学生を採ろうとしています。こういう人材は、実はマッキンゼーのみならず、どこの企業にとっても欲しい人材です。
本書のメインはこのリーダーシップについての解説で、次のように分かりやすく解説してあります。
『本来のリーダーとは、自分の主張を押し通そうとする強引な人ではなく、「チームの使命を達成するために、必要なことをやる人」です。』
『リーダーがなすべきこと
①目標を掲げる
②先頭を走る
③決める
④伝える 』
つまり、リーダーシップは役職が高い人にだけ必要な力ではなく、スタッフであっても求められる力です。そのため、大学時代からこのリーダーシップの発揮を意識しながら行動していると、企業にとって魅力的な人材に育ちます。
リーダーシップは部活の主将やサークルの代表をやらないと身に付かないと思いがちですが、この本を読むと役職は関係ないということが分かります。この本は就活に直接関係する本ではありませんが、リーダーシップを身につけるにはどうすればいいのかというヒントが書いてありますので、結果的に就活に役立つ内容です。リーダシップは本を読んで身に付くものではなく、いろいろなことを実践・経験して身に付くものです。力をつけるには時間がかかります。そのため、就活を始めてからというよりもっと早い段階(例:大学1年生)で読んでおくといい本としてお勧めします。