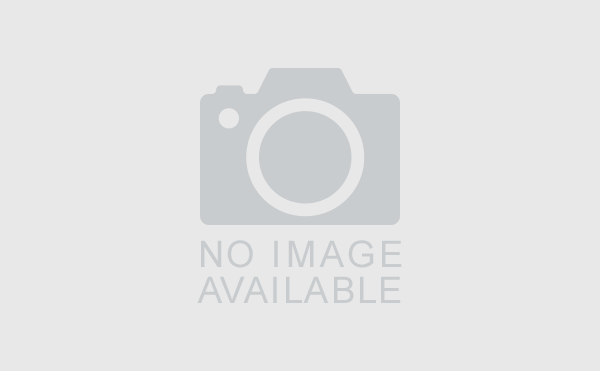これからの採用論
新卒採用の今後の構造の変化
近年、新卒採用の割合が減少し、中途採用の割合が増加しています。5000人以上の大企業では、現在中途採用の比率が約3割となっていますが、近い将来にはさらに増加し、新卒採用が5割、さらに10年後には新卒3割・中途7割という時代が到来する可能性があります。
その背景には、転職が一般化し、優秀な人材が中途採用市場に出てくるようになったということが一つの要因として挙げられます。かつては転職に対するネガティブなイメージが強く、優秀な人材が転職市場に出てこなかったため、新卒採用で優秀な人材を確保しなければ、将来の幹部候補が育たないという状況でした。
しかし近年では、優秀な人材でも転職に対する抵抗がなくなり、大企業からも積極的に人材が流動化しています。そのため、あえて新卒にこだわらなくても、中途採用によって優秀な人材を確保できる時代になってきています。中途採用の人材は即戦力となることが多いので、むしろ中途採用メインの方が効率的とも言えます。
とはいえ、「すべてを中途採用でまかなえばよい」というわけではありません。おそらく、新卒採用による「組織文化を体現する人材層」は、今後も3割程度は維持されると考えられます。なぜなら、最初に入社した企業で受ける企業文化の刷り込みの影響は非常に大きく、その企業の中枢には、文化を深く理解し体現できる社員が「柱」として存在することが、組織の持続的な強さにつながるからです。
スポーツチームを見ても分かるように、優秀な選手を集めただけでは真に強いチームにはなりません。チームを支える「柱となる生え抜き選手」がいてこそ、組織に一体感と長期的な強さが生まれます。企業においても同様に、生え抜きの社員を中心とし、その周囲を優秀な中途採用人材が支えるという構造が、今後一般化していくでしょう。
ただし、「新卒で入社した社員が必ずしも企業に定着するとは限らない」という課題もあります。そのため、3割を新卒採用したとしても、一部は転職していき、10年後に残っているのは2割程度に落ち着くと予測されます。そしてその中から、将来の経営層の中心が育っていくという構造が、理想的で持続可能な企業組織の姿になると考えられます。
今後新卒の採用割合が少なくなっていけばいくほど、採用の外れは許されないので、逆に新卒採用選考におけるいい人材の見極めの重要性は高まっていきます。
現在の新卒採用選考方法の課題と、これからのあるべき姿
現在の一般的な採用選考プロセスは、Webテストとエントリーシート(ES)で候補者を絞り、複数回の面接を通じて段階的に選考対象を絞り込んでいく形が主流です。
ここで問題となるのは、Webテストは対策に時間をかけた人ほど高得点が取れるという点です。つまり「能力の差」ではなく「対策にかけた時間の差」を見ているに過ぎず、また近年対策情報が出回っていることから合格最低点がどんどん上昇しているので、本来なら合格する能力の高い人でも対策をしないと合格しないという状況になっています。企業が採用したいのは、対策に長けた人ではなく能力が高い人なのですが、その選考目的を満たせなくなってきています。
また、ESも、最近ではChatGPTやGeminiといったAIの活用が進んでおり、学生本人の実力を文章 (国語力) から見極めることが難しくなっています。そのため企業も独自フォーマットを増やしてなんとか本来の能力を見極めようと手を変え品を変え対応していますが、その結果、学生は各社固有のES作成に多大な時間を取られるようになっています。
就職活動は現在約1年に及ぶ長期戦となっており、学生生活のかなりの時間が就活に費やされてしまっています。本来、大学時代は、勉強や部活、サークル、留学など、自分の興味関心あることに熱中する時代だと思います。しかし現在は、大学3年の春から就活が始まり、1年間ほぼ就活漬けになっているのが現状です。これは企業側が採用手法を見直さない限り、変わらない問題です。
#大学は好奇心を目覚めさせるところ(「大学での楽しみ方」参照)
そのため、学生の就活の負担を減らしながらも、優秀な人材を的確に見極める仕組みが必要です。「対策すれば有利になる」方式ではなく、「対策の有無に影響されることなく的確に評価できる」採用プロセスが理想です。
この実現にはいろいろな方法があると思いますが、一つの事例として、私が2017年から始めた就活生の選抜コミュニティ「J-CAD」の選考で採用している方法があります。
#J-CADは「自分に合う会社を見つける力をつけ、就職のミスマッチをなくす」ことを目的にした就活生のコミュニティです。
J-CADでは毎年約1000名のエントリー学生の中から24名を選抜していますが、その選考の最初のステップは「自分史」による書類選考です。これは一つの成功体験を書くガクチカESとは異なり、人生全体の流れをざっくり記述してもらうものです。最近はAIが使えるようになり、短時間での作成が可能となりました。自分史の場合、大学時代にフォーカスしたガクチカと違い(面接で人生のどこを突っ込まれるか分からないので)話を盛ることできません。(盛るとその後の面接でバレます。)
2次面接・3次面接もこの自分史に書いてあることについて質問していくだけなので、採用面接でよくある「あなたの就活の軸はなんですか」や「将来やりたいことは何ですか」等の定型質問に対する想定問答の準備は不要です。
また、最終4次面接では、学生からの質問を起点に会話をアドリブで展開していく形式なので、話がどこに行くかは分かりません。そのため、やはり対策は効かず、結果事前準備に時間をかける必要はありません。
Webテストについては、主に学力や論理的思考力を測るために使用されていますが、この部分の評価は、Webテストではなく大学入試の偏差値や大学での成績で代替することができるでしょう。そうすれば無駄なWebテスト対策も不要になります。(なぜ無駄かというと、Webテスト対策が、仕事に必要な力を鍛えることになるとは到底思えないからです)
なお、一部の人気企業においては、限られた内定数に対して大量のエントリー(倍率100倍超)があるため、自分史等の書類選考だけで面接可能数まで絞り込むのは困難なのも事実です。その対処策として、通常採用されているのがWebテストですが、一見能力判定手法として客観性があるように見えるテストが、実は上で述べたように、対策力の判定ツールにしかなりません。そこで考えられるのが「動画」の活用です。
動画選考はすでに多くの企業で導入されていますが、あるテーマについて3分話してくださいというようなケースが多く、話す内容の作成から話す予行演習をする等かなりの事前準備が必要となります。1次選考の目的は面接可能数までの選考対象者の絞り込みなので、評価のメインは自分史とし動画を補完的に使用するのなら、動画では面接の第一印象程度の情報が分かれば十分です。そのため話す内容の重要性はそれほどありません。学生の負荷を軽減する観点からは、事前準備ができず(時間をかけてもしょうがなく)、またテーマに関して事前準備ができない方法が理想的です。
例えば「撮り直し不可の15秒」の短い動画です。動画のお題は毎回違うテーマがランダムに出るようにして、事前の情報収集対策が効かないようにします。また話してもらうテーマを見てから考える時間は15秒として、AIに回答を求める時間がないようにします。一発撮りで作り込みや編集ができない形式にすることで、結果的に学生の動画作成負荷が軽減されると思います。(そして、選考対象絞り込みの情報としてはこれで十分です。)なお、ここで大事なことは、評価のメインは自分史で行い、動画は補完的に使用すると学生に伝えることです。学生が、評価のメインは動画だと誤解すると、例えば15秒で話す練習に時間をかけるというような無駄な対策をするようになります。
また、選考に社員のマンパワーを投入できる場合は、例えば上記方法の最終面接の前に短期グループワークを入れて学生の動きを見るようにすればさらの選考精度を上げることがでしょう。(但し、ワークは3日もやれば十分です)
以上の対策の効かない採用選考プロセスをまとめると次のようになります。
| 現在の方法 | これからの提案 |
| Webテスト | →入試偏差値や大学での成績で代替、必要な場合ショート動画を導入 |
| ES | →自分史の提出 |
| 面接(定型質問) | →自分史に記載内容について質問 |
| 最終面接 | →逆質問からの自然な対話 |
これはあくまで一つの例ですが、仮にESが共通フォーマットの自分史に置き換わるだけでも、就活生の負荷は激減すると思います。
学生が就活にかける時間を節約できるようにするにはどうすればいいか。各企業の採用担当の方の知恵の絞りどころだと思います。(期待してます!)
補足:自分史を選考に使う場合の今後の注意点としては、以前は文章力などから学生の能力を判断できましたが、AI活用が一般化した現在では、国語力の差は見えづらくなっています。そのため、その人のこれまでの人生の節目節目での判断、行動等から、人生の流れの良し悪しを見て、今後の成長ポテンシャルを評価することが必要です。
参考:東京大学の学内広報誌「淡青評論」(2025年6月24日発行)に掲載された松尾豊教授のコメント
『学生による生成AIの活用も急速に進んでいます。いろいろな人の話から総合的に推測するに、学生は社会のなかで最も生成AIを活用しているカテゴリのひとつだと思います。課題提出やテスト準備の場面で、おそらく私たち教員が気づかないほど徹底的に活用されています。オンラインテストを生成AIを使って答えるという「悪い」使い方もされていると思いますし、生成AIを使って課題提出のレポートも作成されています。さらには、それが生成AIで作ったものだとバレないような工夫も頑張っているはずです。そして、口頭試問に備えるため、レポート内容を自分に分かりやすく説明させるといった使い方もされているでしょう。あるいは、講義資料や教科書を読み込ませ、要点を自分に説明させ、分からないところについて対話することで、文章全体を読まなくても短時間で効率的に内容を掴むということも行われているはずです。
こうした学び方は、「手を抜いている」と見えるかもしれません。しかし考えてみると、政治家や経営者などの社会の重要な意思決定者は、「レク(レクチャー)」を受けることが当たり前です。会議前に担当者から要点の説明を受け、いくつか質問を交えて理解を深めます。こうした短時間での効率的な知的インプットの方法を、学生も個人で実現できるようになったと考えることもできるのではないでしょうか。学び盛りの若い時代から、こうした「レク」を自由自在に受けることができれば、科学技術全体、社会全体に対しての俯瞰的な理解、総合的な理解が我々の世代よりもずっと進むのかもしれません。』