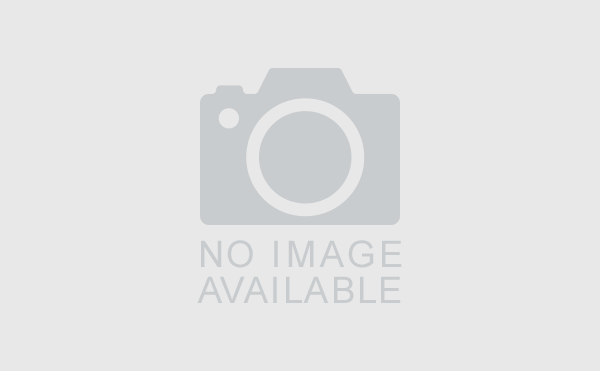0と1の間
MITにMedia Labという有名な研究所があります。Media Labで1970年代後半に行われた研究に「Talking Head Projection」という有名な研究があります。
 「Talking Head Projectionは、テレプレゼンス(遠隔臨場感)を強化するための実験でした。このアイデアは、ディズニーのホーンテッドマンションで人気のある「頭部プロジェクション」の発展形です。そこでは、女性の動く映像が顔の形をしたスクリーンに投影され、真の3D効果が生まれます(誤って「ホログラフィー」と呼ばれることもあります)。Talking Head Projectionでは、上下左右に動くジンバルに取り付けられた、動く顔型スクリーンを使用しました。このスクリーンの動きは、被写体となる人物の実際の頭の動きによって駆動されます。撮影時には、その動きが画像と音声とともに記録され、すべてがスーパー8フィルムに収められました。」
「Talking Head Projectionは、テレプレゼンス(遠隔臨場感)を強化するための実験でした。このアイデアは、ディズニーのホーンテッドマンションで人気のある「頭部プロジェクション」の発展形です。そこでは、女性の動く映像が顔の形をしたスクリーンに投影され、真の3D効果が生まれます(誤って「ホログラフィー」と呼ばれることもあります)。Talking Head Projectionでは、上下左右に動くジンバルに取り付けられた、動く顔型スクリーンを使用しました。このスクリーンの動きは、被写体となる人物の実際の頭の動きによって駆動されます。撮影時には、その動きが画像と音声とともに記録され、すべてがスーパー8フィルムに収められました。」
アメリカが核攻撃を受けた場合、大統領や国務長官などアメリカのトップリーダー5人は、それぞれが最寄りの米軍基地の地下核シェルターに避難して、ビデオ会議で直ちに反撃するかどうかの高度の意思決定をする必要があります。通常のビデオ会議ですと、全員が一つの場所にいるときと同じようにコミュニケーションをはかることは難しく、結果として意思決定品質が低下するので、その課題解決のため、リモートでも臨場感のある会議ができるようにするための研究が行われました。ちなみにこの研究のスポンサーは国防総省先端技術研究計画局 (DARAP) でした。
研究の結果、発明したのは次のような方法でした。
会議に参加する人のそれぞれの顔の形をしたプラスチックのレリーフを作り、そこにリモートカメラが撮影している顔の映像を裏から投影して映すというものです。5人の人々は、それぞれまったく違った場所で、予め決められた順番に座ることになります。私の場所では、私は生身の人間だが、右隣に座っているあなたはプラスチックで、あなたの場所では、私の方がプラスチックで、あなたの左隣に座っているという具合です。
このレリーフは左右上下に動くジンバルに固定されており、その人の顔の動きに同期して動きます。つまり向こうでうなずくと、こちらのレリーフもうなずきます。またお互いに向き合うこともできます。私とあなたがお互いに顔を見ながら話をしているとき、テーブルの向こう側にいる誰かの顔が口をはさんだら、私たちは話を止めて、その顔の方を向くはずです。
半立体のレリーフに映像を投影し、実際にしゃべっている人の顔を投影すると、顔の形のスクリーンは硬いにもかかわらず、たしかに唇が動いているように見えたそうです。これは特にハイテクというわけではないですが、ローテクをうまく使って問題解決をした良い事例だと思いました。
何かの課題があったときに、それに真正面から向き合って根本的に解決しようとすると、現在の技術ではなかなか解決できないということがよくあります。そういう時に、既存のテクノロジーをうまく組み合わせることによって、課題を解決できる場合があります。このことを私は「0と1の間に答えがある」と呼んでいます。(1 =画期的な発明により課題を解決した状態、0=課題は解決されず結果的に現状と変わらない状態)
研究開発の現場において、1を目指して新技術の開発に取り組むのですが、結局実用化できず成果は0のままということがよくあります。そういうときに0と1の間を狙ったアプローチをすると意外とうまくいくことがあります。
最近見つけた0と1の間の事例として目から鱗だったのが、かってヒットした漫画「サラリーマン金太郎」のYouTube版です。
通常漫画をYouTubeに載せるとなるとアニメ化するというのが一般的ですが、その場合アニメ用に作画するので、どうしてもオリジナルの絵が再現されず、何か違うなという違和感が残ります。
今回画期的だと思ったのは、アニメ化するのではなく、漫画の絵をそのまま利用して、その吹き出し及び効果音のところを音声に置き換えるという方法です。このYouTube版を観て面白いなと思ったのは、絵は(そのまま使っているので当たり前ですが)まさに漫画そのものなので、当然ながらクオリティーは担保されており、また吹き出しの部分が大人は大人の声、子供は子供の声できちんとアテレコされているので、まるで漫画を読んでるかのように(いやそれ以上に臨場感があって)面白いなと思いました。
また、音声は受動的に耳に入ってくるので、画面に能動的に集中することができ、各シーンの絵のクオリティをじっくり鑑賞できます。(作者の絵のうまさが分かります。)漫画を読んでいるときには、吹き出しを読むことにも注意力を使うので、今回のように1枚1枚の絵のクオリティをじっくり楽しむ余裕はありませんでした。
0を元の漫画、1をそのアニメ化したモノと捉えると、今回のYouTube版は0.5と言えますが、0にはない新しい価値を創造しているなと思いました。
元の漫画の絵をそのまま使い、吹き出し及び効果音の部分を音声に置き換えるだけなので、アニメ化にくらべて圧倒的に低コストで作成できますし、さらに漫画を読むのではなく、漫画を観るという新しいジャンルを創造しているので、最初に思いついた人は凄いなと思いました。
画期的な技術が新しいモノを作ると考えがちですが、既存の技術の新しい活用方法に実は多くのチャンスが眠っていると思います。言われてみれば当たり前のことを、最初に閃いて実行する。これが今度ますます重要になると思います。